介護サービスを受けるには
要支援・要介護に認定された人は、介護保険により介護サービスが利用できます。在宅でサービスを利用する場合は、居宅介護サービス計画(ケアプラン)の作成が必要となります。
ケアプランは、要介護度に応じた支給限度額内で、どのようなサービスをどのように組み合わせて利用するのかを、本人の心身の状態や希望にそってたてます。
ケアプランは、自分(家族)で作成、もしくは要支援1・2の人は担当地区の地域包括支援センターに、要介護1~5の人は居宅介護支援事業者に依頼して作成してもらいます(自己負担無し)。依頼する場合は「居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書」を担当のケアマネージャーに提出して下さい。 施設に入所する場合には、「居宅サービス計画作成依頼届」の提出は必要ありません。
サービス計画作成事業者一覧
サービス提供事業者一覧
ケアプラン自己作成
(帳票様式No.1①要支援)
介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書【PDF:91KB】
(帳票様式No.1②要介護)
居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書 【PDF:87KB】
要介護1~要介護5
【記入例】(第1表)居宅サービス計画書(1)【PDF:221KB】
【記入例】(第2表)居宅サービス計画書(2)【PDF:264KB】
【記入例】(第3表)週間サービス計画表【PDF:188KB】
【記入例】(第4表)サービス担当者会議の要点【PDF:231KB】
(第6表)サービス利用票・提供票(兼居宅サービス計画)【PDF:281KB】
【記入例】(第6表)サービス利用票・提供票(兼居宅サービス計画)【PDF:414KB】
(第7表)サービス利用票別表・提供票別表【PDF:160KB】
【記入例】(第7表)サービス利用票別表・提供票別表【PDF:283KB】
要支援1、要支援2
(帳票様式No.2)介護予防サービス・支援計画書【PDF:314KB】
(記入例)(帳票様式No.2)介護予防サービス・支援計画書【PDF:220KB】
(記入注意事項)(帳票様式No.2)介護予防サービス・支援計画書【PDF:374KB】
(帳票様式No.4)介護予防支援経過記録( サービス担当者会議の要点を含む )【PDF:318KB】
(帳票様式No.5)サービス利用票・提供票(兼居宅サービス計画)【PDF:283KB】
(帳票様式No.6)サービス利用票別表・提供票別表【PDF:162KB】
サービスの種類
在宅サービス
- 訪問を受けて利用する
- 訪問介護(ホームヘルプ) 要介護1~5
ホームヘルパーが訪問し、食事、入浴、排泄などの身体介護や調理、洗濯、掃除などの生活援助を行います。通院などを目的とした、介護タクシーも利用できます。 ※要支援1・2の人は「介護予防・日常生活支援総合事業」の「訪問型サービス」を利用 します。詳細はページ下部「介護予防・日常生活支援総合事業」に記載してあります。 - (介護予防)訪問入浴介護 要支援1・2、要介護1~5
介護職員と看護職員が移動入浴車で家庭を訪問し、浴槽を提供して入浴の介護をします。 - (介護予防)訪問リハビリテーション 要支援1・2、要介護1~5
理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問してリハビリテーションを行います。 - (介護予防)訪問看護 要支援1・2、要介護1~5
疾患などを抱えている人について、看護師などが居宅を訪問して、療養上の世話や診療の補助を行います。 - (介護予防)居宅療養管理指導 要支援1・2、要介護1~5
医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが、通院が難しい人の居宅を訪問し、療養上の管理や指導を行います。
- 通所して利用する
- 通所介護(デイサービス) 要介護1~5
通所介護施設で、食事・入浴などの介護や日常生活上の支援、機能訓練などを日帰りで行います。 ※要支援1・2の人は「介護予防・日常生活支援総合事業」の「通所型サービス」を利用 します。詳細はページ下部「介護予防・日常生活支援総合事業」に記載してあります。 - (介護予防)通所リハビリテーション(デイケア) 要支援1・2、要介護1~5
介護老人保健施設や医療機関などで、食事・入浴などの介護や日常生活上の支援のほか、理学療法士や作業療法士などによるリハビリテーションを日帰りで行います。
- 居宅での暮らしを支える
- (介護予防)福祉用具貸与 要支援1・2、要介護1~5
日常生活の自立を助けるための福祉用具を借りられます。
①車いす ②車いす付属品(電動補助装置など) ③特殊寝台 ④特殊寝台付属品(サイドレールなど) ⑤床ずれ防止用具 ⑥体位変換器 ⑦手すり(工事をともなわないもの) ⑧スロープ(工事をともなわないもの) ⑨歩行器 ⑩歩行補助つえ ⑪認知症老人徘徊感知機器 ⑫移動用リフト(つり具の部分を除く) ⑬自動排泄処理装置 ※①~⑥、⑪、⑫の福祉用具は、原則として要支援1・2、要介護1の人は利用できません。 ※⑬の福祉用具は、原則として要支援1・2、要介護1~3の人は利用できません(尿のみを吸引するのものは除く)。※令和6年4月から、次の福祉用具は利用方法(借りる、または購入)を選択できます。⑧のうち固定用スロープ ⑨のうち歩行器(歩行車を除く)⑩のうち単点杖(松葉づえを除く)と多点杖
- (介護予防)特定福祉用具販売 要支援1・2、要介護1~5
同一年度で10万円を上限に、都道府県等の指定を受けた事業所から福祉用具を購入したとき、利用者負担の割合分を除いた購入費が支給されます。
①腰掛便座 ②自動排泄処理装置の交換可能部品 ③入浴補助用具 ④簡易浴槽 ⑤移動用リフトのつり具の部分⑥排泄予測支援機器※令和6年4月から次の福祉用具は利用方法(借りる、または購入)を選択できます。固定用スロープ、歩行器(歩行車を除く)、単点杖(松葉づえを除く)と多点杖
- (介護予防)住宅改修費支給 要支援1・2、要介護1~5
20万円を上限に、手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をしたとき、利用者負担の割合分を除いた改修費が支給されます。
住宅改修の手続きの流れ(償還払いの場合)
1.担当のケアマネジャーに相談をして下さい。
2.市役所東館の長寿福祉課に次の書類を提出します。
・住宅改修着工承認申出書
・住宅改修が必要な理由書
・改修工事の図面
・工事費見積書 ・部材単価のわかる資料
・改修前の状態がわかるもの(改修前の日付入り写真)
・住宅の所有者の承諾書(改修の利用者と住宅の所有者が異なる場合)
3.長寿福祉課から住宅改修を認める通知をします。
4.施行・完成
5.工事完了後、長寿福祉課に次の書類を提出します。
・住宅改修費支給申請書
・領収書
・工事費内訳書
・改修後の状態がわかるもの(改修後の日付入り写真)
6.限度額内の利用者負担の負担割合分を除いた金額が住宅改修費として支給されます。
短期間施設に泊まる
- (介護予防)短期入所生活介護(ショートステイ) 要支援1・2、要介護1~5
介護老人福祉施設などに短期間入所している人に、食事・入浴などの介護や日常生活上の支援、機能訓練などを行います。
- 介護予防短期入所療養介護 要支援1・2、要介護1~5
介護老人保健施設や医療機関などに短期間入所している人に、看護や医療的管理下の介護、機能訓練、日常生活上の支援などを行います。
在宅に近い暮らしをする
- (介護予防)特定施設入居者生活介護 要支援1・2、要介護1~5
有料老人ホームなどに入居している人に、食事・入浴などの介護や日常生活上の支援、機能訓練などを行います。
施設サービス
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) 要介護1~5 常時介護が必要で居宅での生活が困難な人に、食事・入浴などの介護や日常生活上の支援、機能訓練、療養上の世話などを行います。新規入所は原則として要介護3~5の人が対象です。
- 介護老人保健施設(老人保健施設) 要介護1~5 病状が安定し在宅復帰をめざしている人に、看護や医学的管理下の介護、機能訓練などを行います。
- 介護医療院 要介護1~5 長期療養を必要とする人に、生活の場としての機能もそなえた施設で、医療と介護を一体的に行います。
地域密着型サービス
- (介護予防)認知症対応型共同生活介護(グループホーム) 要支援2、要介護1~5
認知症の人を対象に、共同生活をする住宅で食事や入浴などの介護や日常生活上の支援、機能訓練などを行います。 - (介護予防)認知症対応型通所介護 要支援1・2、要介護1~5
認知症の人を対象に、食事や入浴などの介護や日常生活上の支援、機能訓練など専門的なケアを日帰りで行います。 - (介護予防)小規模多機能型居宅介護 要支援1・2、要介護1~5
通所を中心に、利用者の選択に応じて訪問や短期間の宿泊を組み合わせた滞納なサービスを行います。 - 看護小規模多機能型居宅介護 要介護1~5 小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合わせて、通所・訪問・短期間の宿泊で介護や医療・看護を行います。
- 地域密着型通所介護 要介護1~5 定員が18人以下の小規模な通所介護事業所で、介護や日常生活上の支援、機能訓練などを行います。
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 要介護1~5
定員が29人以下の小規模な介護老人福祉施設で、介護や日常生活上の支援、機能訓練などを行います。新規入所は原則として要介護3~5の人が対象です。
介護予防・日常生活支援総合事業
介護予防・生活支援サービス事業 事業対象者、要支援1・2
- 訪問型サービス ホームヘルパーによる食事・入浴などの介助や、掃除・洗濯などの生活援助 民間企業やボランティアなどによる掃除・洗濯などの生活援助 保健師などの専門職による居宅での相談や指導などの短期集中予防サービスなど
- 通所型サービス 通所介護施設などでの食事・入浴などの介助や機能訓練 民間企業とボランティアの補助によるミニデイサービス、運動、レクリエーション活動 保険・医療の専門職による生活行為改善のための短期集中予防サービスなど
- その他の生活支援サービス 見守りや栄養改善を目的とした配食サービス 地域住民やボランティアが主体となり、定期的な安否確認や緊急時の対応を行う見守り サービス 訪問型サービスや通所型サービスと一体的に提供する、自立支援に役立つ生活支援
【R4.10】御殿場市総合事業サービスコード【PDF:375KB】
一般介護予防事業 65歳以上の人
介護予防に関するパンフレットの配布や講座・講演会などの開催
地域住民が主体となって行う介護予防活動の支援や、介護予防をサポートするボランティ
アの育成など
介護保険サービスを利用したときは
費用の1割、2割、または3割を負担します
居宅介護サービスは、原則としてケアプランに沿って利用します。サービスを利用したときは、サービス提供事業者にサービス利用票と被保険者証を提示し、かかった費用の1割、2割または3割を支払います。また、利用できるサービスは、介護度によって、上限額(区分支給限度基準額)が定められています。上限額を超えた分は全額利用者負担となります。
また、在宅で受けられるサービスのうち、福祉用具購入費の支給及び住宅改修費の支給は、いったん全額自己負担となり、申請によって後日9割、8割、または7割を市から支給する「償還払い」の制度と、費用を全額事業者に支払うことが困難な場合は1割、2割、または3割の自己負担額だけ払い、残りの9割、8割、または7割を市から事業者に支払う「受領委任払い」の制度があります。
なお、「受領委任払い」の支払い方法を利用するには、市と受領委託払い契約をしている事業者を利用してください。
利用者負担が高額になったときは高額介護サービス費が支給されます
利用者が同じ月内に受けた、在宅サービスまたは施設サービスの利用者負担の合計(同じ世帯に複数の利用者がいる場合は、世帯合計額)が、利用者負担の上限を超えた場合,申請により市が認めた時は、超えた分が高額介護サービス費として支給されます。
また、住民税世帯非課税の人は、所得に応じて個人単位の上限額が設定されます。
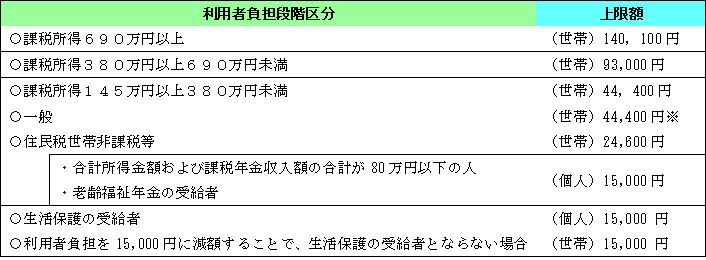
サービス支給限度額は
介護保険で利用できる居宅サービスは、要介護度によってどのくらい利用できるのかが決まっています。これを居宅サービス区分支給限度額といいます。
居宅サービス区分支給限度基準額
| 区分 | 一カ月の区分支給限度基準額 |
| 要支援1 | 50,320円 |
| 要支援2 | 105,310円 |
| 要介護1 | 167,650円 |
| 要介護2 | 197,050円 |
| 要介護3 | 270,480円 |
| 要介護4 | 309,380円 |
| 要介護5 | 362,170円 |
※限度額の範囲内でサービスを利用するときは、利用者負担はサービス費用の1割、2割、または3割です。限度額を超えて利用した場合は、超えた分が全額利用者の負担になります。基準額の範囲内の利用者負担額は、この内の1割ですが、基準額を超えたサービス分は、全額自己負担となります。
その他、要介護度に関わらず支給限度基準額が定められているものがあります。
福祉用具購入費=10万円(期間は1年間)、住宅改修費=20万円(改修時に住んでいる住居について)
問い合わせ
長寿福祉課
TEL:0550-82-4134

